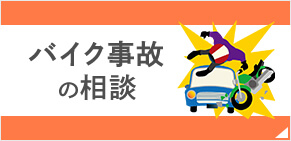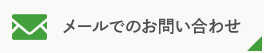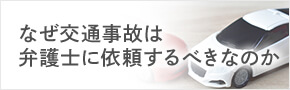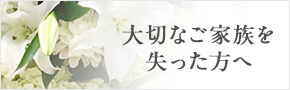腓骨骨幹部骨折 偽関節 癒合不全 長管骨変形 後遺障害12級8号認定事例
(令和7年9月30日原稿作成)
腓骨の骨幹部骨折で注意するべきこと
■下腿(かたい)とは
ひざの関節から足首の関節までの部分をいいます。
■脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)とは
下腿には、脛骨と腓骨という長い2本の骨があります。太い方が脛骨、細い方が腓骨です。
■脛骨、腓骨の骨幹部骨折
骨幹部とは、かんたんい言いますと、骨の端ではない部分です。
脛骨、腓骨の骨幹部の骨折については、当法律事務所がご相談やご依頼をお受けした中で、バイクに乗って交通事故に遭い、転倒してこの骨折を受傷するケースが多いですし、脛骨骨幹部と腓骨の骨幹部の両方を骨折してしまうケースも多いです。
この部分を骨折すると、後遺障害が残るおそれがあります。特に、痛みやしびれが残ったり、折れた骨のくっつきの状態
などを確認していくことが自賠責保険後遺障害との関係で重要になってきます。
以下の事例は、歩行中に車に衝突されて転倒し、脛骨骨幹部、腓骨骨幹部の両方を骨折してしまったケースをご紹介いたします。
事例の概要
被害者は(70代女性)、徒歩で道路を横断し、もう少しで横断を終えるところだったのですが、右折してきた車に衝突され、路上に転倒し負傷しました。
被害者は病院に救急搬送され、検査の結果、脛骨腓骨骨幹部開放骨折と診断され、その病院に入院することになりました。
骨折の程度がひどく、脛骨には髄内釘という釘が入れられ、腓骨にはキルシュナー鋼線という金属の線が入れられました。
被害者は、術後すぐにリハビリテーションを実施することになり、事故から1ヶ月で退院することになりました。退院後もこの病院で外来(通院)リハビリテーションが続けられることになりました。
脛骨の骨折については順調に骨がくっついていきましたが、腓骨・脛骨の折れた部位の痛みなどの神経症状については続いており、残りました。
腓骨に入れられた金属線については抜くことになったのですが、被害者は、腓骨の骨折部分は偽関節化しているとの指摘を受けたようでした(つまり、折れたところのくっつきがどうも進んでいないようでした。)。
腓骨の金属線が抜かれ、傷口の処理をされて症状固定となりました。
症状固定までの治療期間は8ヶ月弱でした(うち、入院が1ヶ月ありました。)。
後遺障害診断書の記載
■自覚症状欄
骨折部分の疼痛などの記載がありました。
■精神・神経の障害 他覚症状及び検査結果の欄
患側(=受傷した下肢の側)の足底の筋力が軽度低下があるという記載になっていました。MMT(徒手筋力検査といいます。)は 4 と記載されていました。
※徒手筋力検査というのは0から5の6段階で判定し、5は強い抵抗を加えても運動域全体にわたって動かせるという評価であり、4は抵抗を加えても運動域全体にわたって動かせるという評価になります。これをもとに、軽度筋力低下という評価をされたものと考えられます。
■下肢長を記載する欄
下肢の短縮が生じているかどうかを確認する検査です。
患側82.5cm 健側83.0cmと記載されていました。
下肢の短縮については0.5cmの差は後遺障害等級に該当するような差にはなりません。
※下肢の短縮については、数値上の差を確認すること以外に、そもそもそのような差が出てくる医学的原因がはっきりしていることが必要になります。
■足関節とひざの関節の機能障害の欄
いずれも左右差はほどんとありませんでしたし、両側とも参考可動域角度とほぼ同程度の可動域が得られている記載になっていました。
■障害内容の増悪・緩解の見通しの欄
腓骨骨幹部については偽関節状態であるが、今後長期経過で癒合してくる可能性があり、疼痛も改善してくると考えている旨の記載がありました。
以上から推測される後遺障害等級は?
以下のとおりの結果が推測されます。
●後遺障害非該当
●骨折部の疼痛が残ったものとして後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)
●折れた腓骨骨幹部の偽関節が認められて後遺障害12級8号(長管骨に変形を残すもの)
後遺障害等級のチェックで金田総合法律事務所ができること!
上記のとおり、本件は後遺障害非該当となるおそれもありますが、後遺障害12級8号が認定される可能性もあると考えられるケースです。
ここで被害者からご依頼をお受けした弁護士が何をするべきか? ということですが、重要なのは、画像上、骨折した腓骨骨幹部が偽関節の状態になっているのかどうか の確認です。
なぜなら、後遺障害12級が認定される見込みがあるのかどうかを確認するには、この骨の状態を確認する必要があるからです。
そして、この骨の状態を確認するためには、後遺障害等級認定を申し立てるために取り寄せた画像CD-Rを確認する必要があります。
ポイントになるのはCT画像です。
本件では、交通事故から7ヶ月弱の時点で検査をされたCTの画像がありました。当法律事務所弁護士はこのCT画像を確認しました。
以下は、このCT画像のうちの1枚です。

縦に長い物体が腓骨ですが、この腓骨が折れてつながっていないと考えられるところがあります。つまり、事故から7ヶ月弱経過しても、折れた骨のくっつきが進行していないように見受けられます。
もちろん、この縦断面画像だけで偽関節になっているかどうかを判断できるものではありません。当法律事務所弁護士は、腓骨の骨折部分の縦断面全体を確認しましたところ、どの部分についても腓骨の折れた部分がくっついていないのでは?
と考えました。
そこで、当法律事務所では、このCT画像のうち腓骨骨折にかかわる部分の縦断面を全て印刷整理し、自賠責保険会社に対して、この骨折部分全体を確認していただきたい旨の文書を作成し、後遺障害診断書などと一緒に自賠責保険に提出しました。
ただし、場所によっては折れた腓骨がくっついているか、いないか、微妙なところもありましたので、結局は自賠責保険がどのような判断・決定をするかどうかを待つしかありません。
後遺障害等級認定結果~12級8号が認定~
自賠責保険は、提出の画像上(もちろん、画像CD-Rも提出しております。)、腓骨骨幹部の偽関節(ぎかんせつ)が認められ、腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すものと捉えられることから「長管骨に変形を残すもの」として後遺障害12級8号に該当する旨判断しました。
※骨折部分の痛みなどについては、上記の後遺障害12級8号に含めての評価となりました。
偽関節(=示談書自賠責保険の認定要件と考えられる意味での偽関節のことです)となっているかどうかが微妙なケースでしたが、自賠責保険は偽関節となっていることを認定しました。
被害者はこの自賠責保険行為所具合12級認定により224万円の支払いを受けることができました。
最終示談交渉
自賠責保険で後遺障害12級が認定された後、相手方と最終示談交渉に入りました。
被害者側からは、入院雑費、通院付添費、家事労働の休業損害、後遺障害逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などを請求しました。
結果、示談で合意ができ、最終で450万円 の支払いを受けることができました。
上記自賠責保険からの224万円とあわせて弁護士受任後、674万円 の支払いを受けることができました。
最後に
●症状が残った場合、どのような後遺障害等級が認定される可能性があるか
●これらの認定される可能性がある後遺障害等級の見通しを確認するためには何をしなければならないか
交通事故でけがをした被害者の弁護士活動は、これら上記のことまで踏みこんでしなければならいと考えております。
事故でけがをした被害者は、財産的な不利益を受けることになりますが、ケガの程度が大きいと、財産的不利益を受ける程度も大きくなってしまいます。
この財産的な不利益をどこまで回復できるかは、交通事故後遺障害問題を取り扱う弁護士の力量にかかっているといっても過言ではありません。
交通事故でケガをし、骨折をされた方は、ぜひ、当法律事務所にご相談ください。
執筆者

最新の投稿
- 2025.12.0214級交通事故後の耳鳴(頭部所見や骨折なし) 後遺障害14級認定事例
- 2025.11.259級10代男性 線状痕の外貌醜状 後遺障害9級認定 1435万円獲得事例
- 2025.09.3012級腓骨骨幹部骨折 偽関節 癒合不全 長管骨変形 後遺障害12級8号認定事例
- 2025.09.2512級ひじ 内側側副靱帯損傷 関節可動域制限 後遺障害12級6号認定 弁護士受任後1174万円を得る