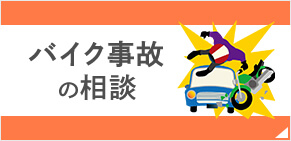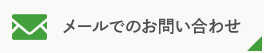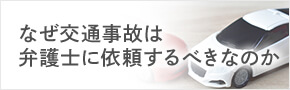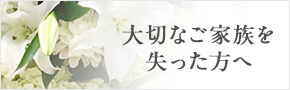ご家族がバイク事故で意識障害が生じたり意識不明となった場合
(令和7年4月25日原稿作成)
「意識」とは?
医学的な定義だけでなく、哲学的な定義もあることばです。
漢字二文字のみですが、その意味を考えるととても深く、難しいものです。
交通事故のケガとの関係では、かんたんに、
自分と環境についてわかっている状態が意識清明である
というふうに理解をしていただければと思います。
逆に言えば、自分と環境についてわかっているとはいえない状態は、意識障害として考えていくことになります。
交通事故で意識障害が問題となるケースとは?
自分と環境についてわかっているかどうかについては、脳にかかわってくることなので、交通事故で頭部や脳を受傷したときに問題となります。
意識障害の程度
意識障害といっても、程度の大小や、その障害がどのくらい継続していたか(しているか)という点で、違いがあります。
意識障害の程度や継続時間といったことがらは、交通事故被害者に残るおそれのある後遺障害の程度にも影響してくる可能性があり、重要です。
■意識障害の程度の評価・判定の仕方(以下、2つの方法を紹介します。)
JCS(ジャパン・コーマ・スケール)という評価方法
意識障害の程度を以下のとおりに分けて判定していく方法です。数字をつけて判定していきます。
1 被害者への呼びかけ、大声をかける又は体をゆする、被害者に痛みを感じるような刺激を与えて、被害者が覚醒(開眼)するかどうか
(1)覚醒(開眼)しない場合でも、以下の反応があるかどうかをみます
・被害者は全く反応しない
・被害者は少し手足を動かしたり、顔をしかめる
・はらいのける動作をする
(2)覚醒(開眼)する場合
・痛みを感じる刺激を与えると被害者は開眼するが、やめると眠り込む
・大声をかけ又は体をゆすると被害者は開眼するが、やめると眠り込む
・呼びかけで被害者は開眼するが、やめると眠り込む
2 被害者への呼びかけ、大声をかける又は体をゆする、被害者に痛みを感じるような刺激をいずれもしないで、被害者が覚醒(開眼)している場合
・被害者が自分の名前、生年月日がいえない
・被害者は現在の年、月、日、時間、いまいる場所がわからない(←見当識障害がある状態です。)
・被害者はだいたい意識清明であるが、今ひとつはっきりしない
GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)という評価方法
開眼、運動機能、発語といった3つの要素につき、点数をつけて意識障害を判定していく方法です。
1 開眼
・自発的に被害者が開眼する 4点
・呼びかけることによって被害者が開眼する 3点
・痛み刺激を与えて被害者が開眼する 2点
・開眼しない 1点
2 運動機能
・命令にしたがい被害者は四肢を動かることができる 6点
・痛みや刺激の部分を被害者は認識する(手足を持ってきたり、はらいのける) 5点
・痛みや刺激を被害者は避けるように四肢を屈曲する 4点
・痛みや刺激に対し被害者は四肢を異常屈曲させる 3点
・痛きや刺激に対し被害者は四肢を伸展させる 2点
・痛みや刺激を加えても被害者はまったく動かない 1点
3 発語
・被害者は現在の年、月、日、場所がわかる 5点
・被害者は会話が混乱している 4点
・被害者は言語が混乱している 3点
・被害者は理解できない言葉を発する 2点
・発語がない 1点
上記3つの要素の満点は15点です。15点であれば意識清明ということになります。
■意識不明とは…呼びかけをしたり、刺激を与えても、被害者は、目を覚まさず、反応も一切ない状態のことを、よく「意識不明」と呼んでいるようです。
家族がバイク事故にあい意識障害が出たり意識不明となってしまったら?
■バイク事故にあい、頭部を受傷し、幸い命が助かっても、意識不明となったらどうなるのでしょうか。
以下の6つの項目に該当し、それが3カ月以上継続して固定している状態は、遷延性意識障害(植物状態)といいます。
・自力で移動できない
・自力で食物摂取できない
・糞尿失禁状態にある
・目で物を追うが認識できない
・簡単な命令に応じることもあるが、それ以上の意思疎通はできない
・声は出ても意味のある発語ではない
遷延性意識障害となれば、治療をほどこしても、回復はきわめて見込みづらいといえます。
被害者は、いわゆるねたきりの植物状態が生涯続くものとして、ご家族は被害者の生活を考えていかなければなりません。
自賠責保険の後遺障害等級では1級1号が見込まれます。
1級が認定されたことにより相手方(任意保険会社)からどれだけの賠償金を得られる かが重要になってきます。
■バイク事故にあい、頭部を受傷し、意識障害が出たら
上でのべたJCSで、事故直後に意識清明というには今一つはっきりしない状態が少なくともあったり、 上でのべたGCSで、事故直後に14点以下の評価であった場合、 被害者は、救急搬送時や初診時に、意識障害があったということになります。
次に、この被害者の意識障害が、どのくらいの程度で、どのくらいの期間が継続していたかが問題となります。
意識障害の程度については、このJCSやGCSの点数評価で判断していきます。
JCSやGCSで意識清明となったのがいつか? で意識障害がどれくらい継続していたかを判断していくことになると思います。
退院しても意識清明にならないというケースもあります。
意識障害がある場合、意識のこと以外にも重要なことがらがあります。
たとえば、
●被害者の頭部の画像検査(CTやMRI)異常があるか、あるとしてどのような異常があるか
●被害者に身体的な障害(特に四肢のまひ)が生じているかどうか
●被害者に精神的な障害(たとえば、物忘れ、怒りっぽい、注意力・集中力の低下など)が生じているかどうか
といったことが重要になります。
→高次脳機能障害という問題です。
身体的や精神的な障害があれば、リハビリテーションを行ったり、神経心理学的検査を行うことになると思われます。
被害者に身体的な障害が残った場合にはもちろん、精神的な障害(高次脳機能障害)が残った場合、被害者は、交通事故前にできていた仕事 ができなくなり(労働能力の一部喪失、大部分の喪失など)、仕事のやめなければならなくなったり、配置がえとなったりする場合があります。
そのような場合には、自賠責保険の後遺障害で適正な等級が認定され、相手方(任意保険会社)からどれだけの賠償金を得られるかが重要になってきます。
家族がバイク事故にあい頭部を受傷し、意識障害が出たり、意識不明となってしまったときにするべきこと
■バイク事故にあい、頭部を受傷し、意識不明(遷延性意識障害)となってしまったとき
上でのべたJCSやGCSといったテスト、頭部のCTやMRIといった画像検査では、明らかな異常結果・所見が出ていると思われますし、 被害者の今後の回復が見込みがたいことは主治医の先生から説明されるものと思われます。
そうすると、ご家族としては、以下のことを考えていく必要があります
●今後、被害者を、自宅で介護していくのか(在宅介護)、それとも、施設で介護をお願いするのか
在宅介護の場合、家屋を改造する必要があるかどうか、家族のみで付き添いをしていくのか、職業付添人にもお願いするのかを考えていく 必要がありますし、家屋などの改造費用や職業付添人に支払う費用のことも考えていく必要があります。
施設介護でも、施設に支払う費用のことを考えていく必要があります。
●交通事故の相手方により受けた損害に見合った賠償を得る必要
上記の将来の介護に関する費用をまかなうためには資金が必要になります。
それだけでなく、被害者の将来の労働の損害、慰謝料などといった 点についても、交通事故の相手方から適正な賠償を受ける必要があり、このことを考えいく必要があります。先ほどものべたとおり、自賠責保険の後遺障害等級では1級1号が見込まれます。
●成年後見の申し立て
上記のとおり、家屋改造、職業付添、施設入所をお願いしたり、交通事故の相手方と損害賠償の交渉(示談)や裁判を行う必要があります。
しかし、意識不明状態から改善しない(遷延性意識障害の)被害者は、自分で話をすることができない状態になってしまっています。
ですので、被害者に関して 家庭裁判所に成年後見の申し立てをして、成年後見人を選任する必要があり、このことを考えていく必要があります。
●症状固定時、主治医の先生に後遺障害診断書等の作成をお願いする
●相手方任意保険会社との示談交渉を行う
■家族がバイク事故にあい、頭部を受傷し、意識障害が出たときにするべきこと
●被害者の意識障害について
被害者が退院しても意識清明にならないようなケースは主治医の先生からご家族に対し、この旨の指摘があったり、注意点を指摘されたりすると思います。
しかし、意識清明であるかどうかの判断はかんたんとは言いがたく、実際には意識障害がもう少し長く続いていたのに、より短期間で意識清明と評価されていたケースもあります。
事故後間もない段階での話にはなりますが、たとえば、主治医の先生の面談や看護師の方に、被害者が自分の名前、生年月日、今の時間やいる場所は言えているのかどうかを聞けるのであれば聞いておきたいところです。
また、これも事故後間もない段階での話になりますが、(コロナ禍の影響で入院患者との面会を家族でさえ制限している病院は多いですが)被害者との面会の中で、「自分の名前、生年月日はわかる?」、「今どこにいるかわかる? 今日は何月何日かわかる?」と たずねてみてもいいと思います。
たずねてみた結果、わからないということであれば、看護師さんにでもお伝えいただき、病院側が把握している状況と食い違いがないかを確認したいところです。
※これらをたずねることを超えるほどの意識障害があるなら、病院からご家族に説明があると思います。
なぜ意識障害のことを確認しておく必要があるかといいますと、もの忘れ、怒りっぽい、注意力・集中力の低下といった高次脳機能障害特有の症状が残った場合、後遺障害等級の認定の際、意識障害があったこと重要になるからです。
●頭部画像(CT、MRI)について
交通事故にあい、頭部を受傷したら、おそらくすぐに頭部のCT検査が行われると思います。
主治医の先生の判断により必要に応じてその後も頭部CT検査や頭部MRI検査が行われたりますが、これらの画像検査で異常所見があるか どうかについては主治医の先生との面談でたずねておきましょう(もちろん、患者側から聞かなくても医師の先生から説明があるケースもあります。)。
頭部の受傷については被害者のご家族も重く受け止めておくべきと思います。 ですので、被害者のご家族も一緒になってお話を聞いておかれることをおすすめします。
初期に頭部画像で異常があると言われた場合、少なくとも事故から3カ月は経過した後も画像検査(特にMRI検査)で確認される必要があると思いますが、この検査結果もご家族が一緒に聞いておかれることをおすすめします。このとき、医師の先生が、「新たな所見は出ていません。」とだけおっしゃることもあります。しかし、この言葉には、事故直後からあった所見については変わりなく存在しているという意味も含んでいる可能性があります。
●事故前と事後後の被害者の様子が違うところをメモをとって確認しておく
これはご家族に一番お願いしたい点です。
以下、一例をあげます。
事故後、被害者に、以下のような様子が見られるようになってはいないか注意深く観察してください。
・わすれっぽい
・きのう言ったことをわすれている
・新しいことをおぼえられなくなった
・怒りやすくなった、
・幼くなった
・言われないとしなくなった
・うまくいかなくなったら修正できない
・一つのことをすると他のことができなくなった
・集中力の低下
・注意力の低下
・意欲の低下
・疲れやすくなった、ぼーっとすることが多くなった
医師の先生も看護師の方も、事故前の被害者の様子を知りません。なので、事故前後の比較ができません。
被害者自身も、事故前と自分の状態が違うことを認識できていないことが多いです。
とすれば、事故前後の被害者の様子の違いに気づくのはご家族しかないのです。
●事故前と事後後の被害者の様子が違うところがあれば、次の診察時にご家族が同席し、主治医の先生にこれをお伝えいただく
●症状固定時、主治医の先生に後遺障害診断書等の作成をお願いする
●相手方任意保険会社との示談交渉を行う
家族がバイク事故で意識障害が出たり、意識不明となってしまったときに受け取れる可能性のあるお金は何?
●治療関係費のうち相手方の過失割合分(相手方任意保険会社が直接医療機関に支払っている場合で被害者側にも過失がある場合は、 通常は最終の金額交渉段階で被害者側の過失を考慮して計算していきます。)
●将来治療費
症状固定となった後の治療費は原則として相手方から賠償を受けることができませんが、症状の内容、程度、治療内容により、必要かつ相当なものは 認められる可能性があります。
特に、遷延性意識障害のケース、高次脳機能障害で後遺障害1級~3級が認定されたケースは、もらさず検討していくべきといえます。
●入院雑費
通常、日額1500円×入院日数で計算して金額を出します。
●将来の雑費
一例をあげますと、意識不明状態(遷延性意識障害の状態)となると、症状固定後もずっと紙おむつが必要になります。
このように将来も継続的に 必要となる紙おむつの費用は認定されます。検討方法、計算方法については、お越しいただいてのご相談とさせていただきます。
●入院通院付添費
入院や通院において付添看護の必要性が認められると、相当性のある期間、大阪の裁判基準では近親者の入院付添につき目安で日額6000円、 通院付添につき目安で日額3000円が認められます。
ただし、近親者が休業して付き添い、これら各日額目安を超える場合には、休業の証明 を取り付け請求していけば、目安を超える金額が認められる可能性があります。
●将来介護費
被害者に介護が必要となる後遺障害が残った場合の症状固定後における付添いに要する費用のことをいいます。
被害者を施設で介護する場合と在宅で介護する場合とで損害の考え方が異なります。
また、在宅介護でも職業付添人に介護をお願いする場合と近親者のみで介護する場合とでも損害の考え方が異なります。
これが認められた場合、被害者の平均余命までの介護費用を考えていくことになりますので、金額が大きくなる損害費目であり、重要な損害費目です。 在宅介護の場合、自宅などの改造費も問題になる場合があります。
●文書料
●休業損害
●入通院慰謝料(傷害慰謝料)
基本は入院通院の日数と期間で金額を出していきますが、他にも考慮すべき要素があります。
●近親者固有の慰謝料
交通事故で被害者が何とか命は助かったけれども、被害者が生命を害された場合に匹敵するような、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときに問題になります。
●後遺障害逸失利益
後遺障害等級が認定された場合、基礎収入(年間の収入)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間 という計算式で損害額を出します。 金額が高額になる可能性がある損害費目です。また、若年の方の場合、かなりの高額になる可能性があります。
●後遺障害慰謝料 認定された後遺障害等級に応じて目安となる金額があります。
バイク事故で頭部を受傷し、意識不明、意識障害となったとき、弁護士に依頼するメリットは?
■被害者が意識不明となった場合
●ご家族としてこれから何をしていけばいいのかを弁護士と相談しながらすすめることができます。
加害者の刑事事件に関し、警察とお話をしたり、加害者本人から連絡があったり、刑事裁判の被害者参加制度を利用するかどうか検察庁から打診があったりします。
病状の説明を受けるため、病院に行くことになりますし、必要であれば付き添い看護をしなければならなくなります(ただし、コロナ禍の影響で家族による面会制限を設けている病院は多いです。)。
上で述べたとおり、成年後見の申し立てをしなければなりませんし、被害者を自宅で介護していくのか、施設で介護していくのかを考えていかなければなりません。
自宅で介護するとなると、 自宅に手を入れる必要があるのかどうか、職業付添人をお願いするのかどうかを考えていくことにもなります。
これらだけでもたくさんの事項があります。
普段の日常生活に加えてこれらのことをしなければならないとなると、ご家族は、心身ともにかなりの負担になるでしょう。 そのような中、弁護士に依頼して弁護士と相談して進めることで、心身の負担はかなり楽になると思われます。
●後遺障害問題で弁護士からきちんとしたサポートを受けることができます。
将来の被害者の介護に関しては多大な費用がかかります。
そのためにも、事故の加害者側から適切は賠償金を得る必要がありますが、賠償金を決めるのに重要な要素として、後遺障害等級の問題があります。
後遺障害等級といってもひとことでかたづくものではなく、主治医の先生に後遺障害診断書を書いていただいたりなど、大切なことがいくつかがあります。
これをもれなくするためには、専門家である弁護士のサポートを受けることは重要です。
●適切な賠償金を得るためには弁護士による示談交渉や裁判などの弁護士活動が有益・重要です。
加害者側の任意保険会社は、弁護士は介入していないケースでは、賠償金を目安よりも低く提案しがちな傾向があります。これを知らずに応じると、後でやり直しはききません。
損害賠償の交渉の専門家である弁護士に依頼することで、不当に賠償金が低いレベルでの解決を防ぐことが可能になります。
■被害者に意識障害が生じた場合
●意識障害となり、高次脳機能障害で後遺障害等級が認定されるべきケースなのに、これを見逃されるおそれを防ぐ点で弁護士に依頼するメリットがあります。
高次脳機能障害が残っても、第三者からそれがわからないことも多いです。
そのため、被害者が高次脳機能障害が残っているにもかかわらず、これが見過ごされ、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されず、 適切な賠償金が得られない不利益が起こるおそれがあります。
高次脳機能障害問題にくわしい弁護士に依頼することで、ご家族がきづかなかったことに気づいていただき、見落としを防ぐことが可能になるといえます。
●ご家族としてこれから何をしていけばいいのかを弁護士と相談しながらすすめることができます。
ご家族の心身の負担を軽減することが可能になります。
●後遺障害の問題や、適切な賠償金を得るために弁護士の介入が有益・重要であることは意識不明のところで述べたとおりです。
ご家族がバイク事故にあい、頭部を受傷し、意識不明、意識障害になってしまったケースは、金田総合法律事務所にご相談ください
金田総合法律事務所では、バイク事故にあい頭部を受傷し、意識不明、意識障害となった案件のご依頼をたくさんお受けしてきております。
そのうち、治療中からご依頼をいただくものが多いです。
全件、弁護士金田が担当しますので、経験不足の弁護士がかかわることはありません。
被害者にとってたよりになるのはご家族です。 ご家族の方におかれましては、金田総合法律事務所に一度お問い合わせいただければと思います。